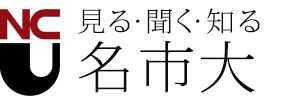在学生の声

ものづくりよりも、大切なこと
映像や音響から情報通信、各種デザイン、建築、環境、インテリアまで、「芸術」+「工学」という名が示す通り、本学の芸術工学部が研究対象とする分野は実に多彩だ。しかしどの分野に進んだ学生も、この学部を選んだ理由を尋ねると似た答えが返ってくる。曰く「ものをつくるのが好きだから」。
芸術工学部では1年生のカリキュラムに早くも実習が用意され、学生は自分の力でものをつくる楽しさと大変さを実感する。それともう一つ、彼らが実習を通して実感することがある。それは、ものをつくる前に、徹底して「考える」というプロセスが不可欠だということだ。
中山さんの心づかい
建築都市デザイン学科3年の中山真弥さんは語る。

「実習で最も大切なのは、自分がつくるものに、どれだけ自分の『思い』を込められるかということだと思います」。
同学科では、1年生の早い時期に住宅設計の実習を行う。与えられる条件は、家族の人員構成と土地の広さなど。その家族が暮らす家はどうあるべきか、その場所で生活するには何に気をつければよいかなど、学生は自分で調べられるだけ調べ、徹底的に考えて図面を描き、建築模型を作成する。
その後、美術館、小学校などとテーマは複雑になっていくが、考えてつくるというプロセスが変わることはない。
3年の後期、中山さんが取り組んだのは「図書館と公民館の複合施設」というテーマだった。名古屋市の東山公園付近に実際にあるエリアを想定し、地形や周辺環境などに配慮しながら、二つの公共施設の機能を併せ持つ建物をつくるという難易度の高いテーマである。
「最初に図書館に行き、過去の図書館と公民館の設計図面集を読み込みました。そして僕が考えたのは、図書館と公民館を2つのエリアに分断せず、それぞれの機能を融合させた施設をつくろうということでした」。

彼は3階建ての建物の各階中央部を図書館・公民館のどちらの利用者も使えるオープンスペースとし、その南側と北側に各施設の機能を配置するというプランを考えた。しかも1階と3階は南側に公民館があり、2階は南側に図書館があるというジグザグの構成を採用した。
「図書館を北側に多くしたのは、日焼けによる本の劣化をなるべく防ぐため。2階に図書館を設けたのは、明るいスペースで勉強をする空間も確保したかったからです」。
また、公民館に集まる人たちの「音」をどうするかという問題も、中山さんは公民館の集会場の近くに図書館の幼児向けの図書コーナーを設けるという解決策を提案した。彼がつくった建築模型の細部にまで、中山さんが考え抜いて導き出した「心づかい」が込められている。
油田さんのあたたかさ
情報環境デザイン学科2年生の油田紗藍さんも、実習がここまで「考える」という作業が必要だということに驚いた。彼女が2年生の前期の実習で与えられたテーマは「探す」。

「この時は、身の周りから『探す』という言葉から連想されるシーンを100種類も書き出し、そこから一つを選んで新しいアプリの企画を立てるという実習でした」。
そして彼女が次に取り組んだテーマは「包む」。
「包むという言葉から連想されるものを自由につくるという実習でした。いろいろと悩んだ結果、私は『言葉を包むもの』をつくろうと思いました」。
言葉を包むといっても、さまざまなシチュエーションがあり、さまざまなものが存在する。彼女はそれらを思いつくままに書き出し、一つひとつ検証を加えていった。しかし、どれも過去に似たような作品が多い。そこで彼女は発想を180度転換し、「今まで言葉を包まなかったもの」を探すことにした。そしてたどりついたのが、言葉ではなくお金を包むもの、つまり「ご祝儀袋」だった。
「実際に何種類かのご祝儀袋を購入し、ネットでも調べました。すると、袋の中にはお金しか入れず、メッセージカードは入れない人が多いことを知りました。せっかくならお祝いの気持ちも包んであげたらいいのに……と考えました」。
また、贈られた祝儀袋がそのまま捨てられることが多いというのも悲しかった。そんな彼女の思いが詰まったのが、作品「ご祝儀ばこ」だ。これは小さな箱にお金とメッセージカードを入れて贈るというボックス。この形状なら、もらった後でも部屋に飾っておけるから、捨てられる可能性も低くなると考えたという。

「でも講評では、先生から『そもそもご祝儀袋には、お金をむき出しにしないという心づかいや、包んだ和紙を結び留める水引など、日本ならではの文化や奥ゆかしさがあるけれど、あなたはそこまで調べた?』と指摘され、自分の考えがまだ甘かったことを痛感しました」。
それでも、先生から「発想は面白いし、何よりも油田さんのあたたかい人柄が出てるね」と言ってもらえたことが、彼女は何よりも嬉しかったという。
鈴木さんのこだわり
産業イノベーションデザイン学科の鈴木翔太さんが2年生後期の実習で取り組んだのは「ICON-感性と理性の統合化したマンマシンインターフェイス」というテーマだった。

「この実習では、まずアイデアの起源を幼少期の体験から探し、子供の頃の無意識の行動をヒントにして、まったく異なるものづくりをするというプロセスを体験しました」。
最初に鈴木さんは子供の頃の通学路をビデオカメラで撮影し、幼き日の鈴木少年は何を見てテンションが上がっていたかを調べた。その中で彼が注目したのは、高い枝を見ると手を伸ばして飛びつこうとするという無意識の行動だった。
「そこから着想し、高くて手の届かない場所にある物をコントロールできるデバイスをつくったら面白いと閃きました」。
では高い所にあって、コントロールが必要なものとは何だろう。最初は寝転がったままで部屋の照明を点けたり消したりできるデバイスが頭に浮かんだ。しかし照明のリモコンなら、すでに実用化されて一般家庭でも使われている。ではもっと遠く、人間の手が簡単に届かない場所にある照明ならどうだろう。彼はステージのスポットライトを思いついた。しかし調べてみると、ステージの照明も今やコンピュータで制御されている。しかし、彼は自分の直感にこだわった。コンピュータでも制御できないくらいの照明の制御が求められる場所が必ずあるはずだ……。調べるうちに彼がたどりついたのが、美術館の照明だった。

「美術館の収蔵品は光を嫌うため、展示中の照明の設定は学芸員さんの熟練のノウハウが求められるそうです。その微妙な照明のコントロールを直感的に行うデバイスなら、まだ誰も手がけていないことに気づいたんです」。
彼は美術館の照明に関する本を片っ端から読んで光について研究した。また愛知県美術館を訪ね、展示のない日に館内の照明を見学させてもらったこともある。
「完成した作品は、調整したい照明の方向に先端を向け、照明の向きと位置、照度を3つのつまみでコントロールするというものでした」。
しかし講評の席で、先生から『3つのつまみがあるなら、光源をLEDにしてRGB(光の三原色)をコントロールして色を変えるという方法もあるね』と指摘された。彼にはそれがショックだった。
「正直、そこまで考えていませんでした。僕たちのゼミはプレゼンが2度あるので、次までにもっと深く考えて企画をブラッシュアップします。ここからが本番です」。
仲間と一緒に考える
実習で大切なのは「考える」こと。しかし彼らは、一人で悶々と考えるのではない。芸術工学部の学生がよく口にするように、同学部は伝統的に学生同士のつながりが深い。それはただ学内のあたたかい雰囲気をかもし出すだけでなく、密なコミュニケーションによってお互いが刺激し合い、新しい発想やものづくりに向かうエネルギーが生まれているのも事実である。
芸術工学部では、広い教室の中に3年生と2年生が1年生をはさむ形で机が配置され、学年の境界には低い棚しかない。だから1年から3年までの学生が毎日顔を合わせ、先輩が後輩の作品づくりについてアドバイスし、後輩が疑問に感じたことを気軽に先輩に気軽に質問できる環境にある。
「特に建築模型をつくる時など、1年生に作業をお願いし、泊り込みしてまで手伝ってくれた後輩に、先輩がお礼として何かごちそうしたり、ドライブに連れていってあげたりするのは芸術工学部の良き伝統になっています」と中山さん。
建築模型づくりに動員されるのは同じ学科の後輩だけではない。情報環境デザイン学科の油田さんも、建築模型づくりのお手伝いをお願いされ「面白そうだから」と手伝ったという。
油田さんは、本学科の学生の結束力の強さにも驚いた。
「秋の大学祭『芸工祭』では、3年生が中心となって企画を進め、2年生がサポートをするのですが、みんなとても真剣で、大学祭の後で先輩が感動して泣いているのを見て私も思わずもらい泣きしてしまいました」。
産業イノベーションデザイン学科の鈴木さんは、自分とは異なる専門分野の友人から刺激を受けた。実は美術館の照明を調べようと決めた時、いろんなアドバイスと一緒に美術館に関する多くの資料を提供してくれたのが建築系の友人だった。
「それに、芸術工学部の学生は自分がどれだけ忙しくても、他人が困っていると快く手を差し伸べて手伝ってくれます」と鈴木さん。
そんな仲間のことを、彼は「ただの友人でなく、家族でもなく、まるで『戦友』のようです」と表現する。
そんな多くの仲間たちの中で、彼らは徹底的に考え、自分の思いを深め、ものづくりのプロへと育っていくのだ。