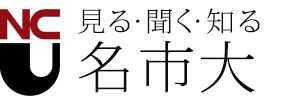在学生の声

それぞれの留学動機
今日の大学教育における重要な課題の一つに、グローバル化する社会に対応できる人材の育成があげられる。名古屋市立大学では世界8カ国の大学と交流協定を締結し、多彩な交換留学・派遣留学プログラムを実施。中には渡航費の補助や単位互換などが認められるものもある。

本学の人文社会学部からも、毎年多くの学生がこうしたプログラムを利用して異文化に触れ、大きく成長して戻ってくる。
国際文化学科の鈴木桃子さんは、1年生の時に「バックネル大学日本語TA奨学生制度」という留学制度があることを知った。これはアメリカ・ペンシルベニア州のバックネル大学で日本語クラスのTA(ティーチング・アシスタント)をしながら授業を受けられるという留学プログラムで、留学費用と奨学金が支給される。高校の頃からアメリカに留学したいと考えていた鈴木さんは、3年生になって卒業後の進路について真剣に考えるようになったことをきっかけに、このプログラムへの参加を決意した。
同様に、部活を引退した時に「このまま大学生活を終わりたくない」と留学を決めたのが現代社会学科の真野ひかるさん。K-POPが大好きで「南ソウル大学交換留学」に応募した。また人間科学科(現心理教育学科)の白井晴子さんも、K-POP好きが高じてもっと韓国を知りたいと思い、2年生の時に南ソウル大学の留学プログラムに応募した。
気持ちを理解してもらえない
彼女たちが最初に突き当たったのは言葉の壁だった。渡航直前、3人ともネイティブの教師や留学生から会話のレッスンを受けた。だがどれだけ日本で学んでも、海外での会話は耳が慣れるまで時間がかかる。
特に大変だったのは、韓国に留学した二人。

南ソウル大学では、前期に語学の授業を受けた。最初、彼女たちは初級クラスに振り分けられた。それでも先生の韓国語はほとんど聞き取ることができなかった。
「でも周囲の人はみな優しくて、筆談をしてくれたり、大きな身ぶり手ぶりでゆっくり話してくれたおかげで、半年ほどで日常会話ならできるようになりました」(真野さん)
「寮の守衛さんが私たちにいろいろ話しかけてくれました。片言で話をするうち、言葉が通じるということは心が通じることだと嬉しかったことを覚えています」(白井さん)
しかし後期になって大学の授業を韓国語で受けるようになると、言葉が格段に難しくなった。
「集中して授業を聞き、理解した言葉を日本語で調べ、ようやく授業の全体を理解していました」(白井さん)
しかし彼女たちが最も苦労したのはコミュニケーションの問題だった。
韓国では、遠慮をしないことが友人関係の証しとされる。二人も韓国の友人から毎日のように食事に誘われた。たまに誘いを断ると『せっかく誘ってるのに!』と機嫌を損ねられることも少なくなかった。
「それに日本人同士なら『今日、ちょっと疲れてるから……』と言えば、行きたくないという気持ちは伝わります。でも韓国で同じことを言うと、友人は『じゃあ元気が出るものを食べに行こう!』と言い、まったく私たちの気持ちを理解してくれませんでした」(真野さん)
彼女たちの前に立ちはだかっていたのは、まさに日本と韓国との“異文化の壁”だった。
自分が日本人であることを思い知る

一方、鈴木さんもアメリカで苦労していた。
彼女が参加したプログラムでは、週に3時間、学生と一緒に授業を英語で受け、週に20時間、日本語クラスのTAとして学生を指導する。最初は周囲と英語で上手にコミュニケーションがとれなかった。しかもその中で慣れないTAの仕事もしなくてはならず、とても大変だった。
「最初の2カ月は、慣れない環境の中で大きなストレスを抱えていました」
その頃、彼女が葛藤していたのは、「本当の自分」と「大学から求められている自分」が違うということだった。
「私も現地の同年代の大学生のように、ラフで自由な雰囲気の中で生活したいと思っていました。でも私はTAの仕事がありました。仕事そのものはとても楽しくて大好きだったのですが、日本語TAには『日本人らしい清楚さ』が求められていたのも確かです」
最初の数カ月、英語がうまく話せないもどかしさにも悩んでいた中で、仕事で求められる「日本人像」にすら上手に対応できない自分がいた。
「生まれて初めて、自分は日本人だったんだということを思い知らされました。同時に、自分の意志とは無関係に、日本人らしさを求められることを何となく窮屈に感じていました」
時を同じくして、東アジア学科の近代史の授業で、彼女は日本の明治時代を学んだ。今から100年前、自由民権や女性解放を求めて戦い続けた人々と、アメリカでアイデンティティを模索する自分の姿が重なって見えた。
異文化を理解するための気づき

韓国で“異文化の壁”を感じた真野さんと白井さんは、この壁を破るにはどうすれば良いかを考えるようになった。
「私は、韓国の友人が何かを言ってきた時、一歩踏み込んで、なぜそう言ったのかを考えるようになりました」(真野さん)
ご飯に誘ってくれるのは、自分を友人だと思ってくれている証拠。そんな相手の気持ちを理解した上で、はっきりと「今日は行きたくない」という気持ちを言葉で伝えることが本当の異文化理解だと気づいたのだ。
「私にとって、それはとても大きな気づきでした」(真野さん)
白井さんも同じ問題で悩み、彼女なりの答えを見つけている。
「異文化の壁を感じていたのは私たちだけではなく、韓国の友人も同じようなことを感じていたと思います。ですから、これは一方的なものではなく、お互いが理解しようと努めることで乗り越えなくてはならないと思いました」(白井さん)
一方、鈴木さんもアメリカで自分自身を見つめながら過ごす中で、多くの気づきがあった。
「アメリカでは、日本人の私はマイノリティでした。それを自覚した時、今までさまざまな分野でマイノリティとして生き辛さを感じてきたであろう人たちに、自分が何の配慮もしてこなかったことを恥ずかしく感じるようになりました」(鈴木さん)
それは単に民族や国際関係だけの話ではなく、さまざまな意味で“弱者”を思いやる視点を得たということでもあった。
留学経験が未来につながる
平成27年春から、鈴木さんは愛知県の公立高校の英語教員に、真野さんは愛知県内の大手自動車関連メーカーへの就職が決まった。
「アメリカの学生に、日本語で日本語を教えたことは、英語教師の仕事をする上で良い経験になると思います。また、異文化の中で苦労したことで、価値観の違いを気にせず、相手を一人の人間として見られるようになったと思います」(鈴木さん)

「留学後、誰かと意見が対立した時など、一歩踏み込んで相手がなぜそう思うのか考えるようにしています。すると、相手の意見も素直に受け入れられるようになりました。私が就職するメーカーは海外にも拠点があるので、いつか海外で仕事を経験し、その成果を日本に還元できるような女性になりたいと思います」(真野さん)
そして遠い将来、企業で働いた経験を教員として活かしたい、と真野さんは夢を語る。
二人より学年が一つ下の白井さんは、現在、就職活動に向けた準備を始めている。
「本当は、留学に行くことをずっと迷っていました。でも覚悟を決めて行ったら、本当に良い経験ができました。留学後、自分のしたいことは何でも積極的に挑戦しようと思うようになりました」(白井さん)
日本に戻った彼女は、本学の学生が発行するフリーペーパーの編集グループに参加した。1年の時から参加してきた、障がいを持つ方と触れあうボランティアサークル「障害者問題研究会」の活動も再開した。美しい文字を書きたくて硬筆習字を習い始めた。洋裁にも挑戦してみた。そして何より、日本についてもっと深く知りたいと思うようになった。
彼女たち3人が留学を通して学んだことは同じではない。しかし、そこで得たことはすべて、これから彼女たちの人生を力強く支えていくに違いない。
(参考) 本学の海外留学プログラムについて
プロフィール
人文社会学部国際文化学科4年生
鈴木桃子さん

高校の頃から英語と外国の文化・歴史・文学・政治などに関心があり、どれか一つに選べなかったため、すべてを学べる人文社会学部に決めた。大学に入学後は平和・戦争に興味を持ち、1年生の頃から地元の平和博物館(ピースあいち)で学生ボランティアを続けている。また平和学習ボランティア団体「PATH」の代表も務める。
人文社会学部現代社会学科4年生
真野ひかるさん

政治学・法学・社会学などを学べて、教員免許も取得できる学部として人文社会学部を選んだ。ハンドボール部ではキャプテン。名市大で良かったと思うことは、決して大きな大学ではないため、「さまざまな個性を持つ人たちが、自分らしく学生生活を送れる環境があること」と語る。
人文社会学部人間科学科(現心理教育学科)4年生
白井晴子さん

名市大で良かったと思うのは、学生同士の仲がとても良いところ。クラスの仲が良いだけでなく、先輩が新入生の面倒をよく見てくれたため、すんなりと大学生活になじむことができた。心理学に興味があって人文社会学部を選んだが、勉強するうちに保育・教育学へと興味の幅が広がってきた。